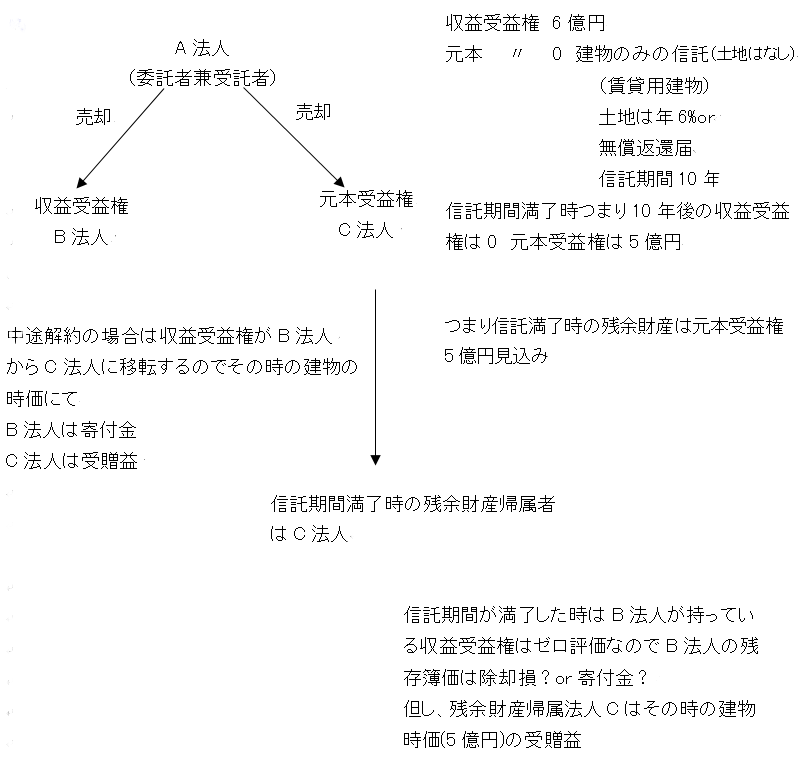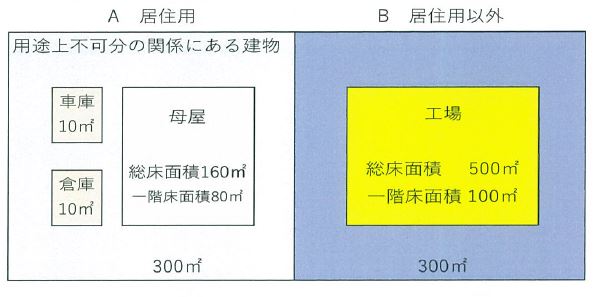《質問》
生命保険の課税関係を教えてください。
特にケース3・4・5がわかりません。
〈契約〉
死亡保険金 2,500万円 現在までの契約経過年数20年
契約者 B
実際の保険料負担者 A(Bの母)
被保険者 B
受取人 C(Bの子)
【ケース1】 Bが死亡した場合・・・・AからCへ2,500万円の贈与に該当し、Cへの贈与税
【ケース2】 仮に契約者を母Aにした場合・・・・ケース1と同じ
【ケース3】 保険料負担者をAがらBに変更した後、Aが3年後に死亡。その後B(被保険者)が10年後に死亡した場合
【ケース4】 Aが死亡し、その時に保険料負担者をBに変更した後、B(被保険者)が10年後に死亡した場合
【ケース5】 保険料負担者をAからBに変更した後、BがAより先に死亡し、その後Aが 死亡した場合
【ケース6】 解約して解約返戻金がBに入った場合・・・・解約返戻金が母(A)からBへの贈与としてBへの贈与税
【ケース7】 現状の契約で、保険料相当をAがBに贈与していると認められた場合
① 年間保険料が110万円を超えれば、支払保険料の金額がAからBへ贈与されたものとして、Bに対して贈与税
② Bが死亡した場合は、Bの相続税