第三回目
《目次》
十六 所得控除
1 医療費控除(添付書類)
2 医療費控除(補てん金)
3 医療費控除(セルフメディケーション)
4 社会保険料控除
5 寄付金控除
6 障碍者控除
7 寡婦控除
8 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
9 所得控除の計算順序
「さくら税研フォーラム」は会員制の税務・会計情報サービスです。法人課税・個人課税・資産課税・消費税等税務全般に渡るポイント、毎年の税制改正の動向など、最新の税務情報を詳しく解説しています。
第三回目
《目次》
十六 所得控除
1 医療費控除(添付書類)
2 医療費控除(補てん金)
3 医療費控除(セルフメディケーション)
4 社会保険料控除
5 寄付金控除
6 障碍者控除
7 寡婦控除
8 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
9 所得控除の計算順序
第二回目
《目次》
九 給与所得
1 ストックオプション等
2 ストックオプションの収入金額
十 退職所得
十一 譲渡所得
1 株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得
2 管理費の扱い
3 贈与時に負担した名義書換料
4 譲渡所得における消費税の取扱い
十二 一時所得
1 店舗に係る損害保険の満期保険金
十三 雑所得
1 国民年金
2 FX取引
十四 損益通算等
1 損益通算
2 土地の取得に要した借入金利子
3 居住用財産の買換え等
4 非居住者である役員の場合
十五 純損失の繰越控除・繰戻し
1 先物取引に係る繰越損失
2 期限後申告での繰越控除
3 純損失の発生年の翌年以後白色申告の場合
4 純損失の一部繰戻
さくら税研では、今週から4回にわたり、個人の確定申告において誤りやすい事項のポイント解説をさせていただきます。
第一回目
《目次》
一 納税地
二 所得の帰属
三 非課税所得
1 遺族年金
2 損害賠償金
四 所得区分
1 車両の売却・下取り
2 立退料の受取り
五 配当所得
1 申告した後の是正
2 申告した後の選択替え
3 利子や配当の申告方法
4 源泉徴収選択口座内の配当等の申告方法
5 外国上場株式の申告
6 住民税の申告
六 不動産所得
1 相続で取得した賃貸不動産の申告
2 共有で所有している物件の貸付けの規模
七 事業所得
1 医師等の所得金額計算特例適用について
2 患者負担金を収受していない場合
3 家内労働者の範囲
4 更正の請求での家内労働者等の所得計算の特例摘要
八 事業所得・不動産所得共通事項
1 消費税の還付金
2 専従者に対し定期保険をかけた場合
3 相続で取得した資産にかかる登録免許税
4 相続で取得した資産にかかる固定資産税
5 少額減価償却資産
6 一括償却資産
7 減価償却方法の届出
8 家事用資産を業務用に転用した場合
9 資産損失
10 青色申告承認申請
11 青色申告特別控除
12 家内労働者の青色申告特別控除
《質問》
30年間にわたり勤務をしていた会社を退職したサラリーマンが、ふるさと納税をしようと考えています。ふるさと納税をした場合、所得税・住民税の減税額を教えてください。
退職金の金額は2700万円(退職所得控除額は1500万円)で、所得税 788,722円が源泉徴収、住民税 600,000円特別徴収されました。
また、退職後も嘱託社員として働き、退職前給与との合計で1400万円を受領する予定です(給与所得控除後後の金額は1180万円)。寄付金を除いた所得控除の金額は合計で300万円、年末調整後の所得税額は 1,417,100円となります(所法78)。
《質問》
土地の賃貸借契約により貸主である地主が受け取る更新料及び名義書換料収入が臨時所得・平均課税の対象となるか否かについてご教示願います。
① 平成30年に土地の借主が変更となり、地主は平成31年までの契約について名義書換料を受取りました。貸付期間が3年未満なので、名義書換料は臨時所得にならないのでしょうか。平成31年に契約を更新し、更新料を受け取った場合には臨時所得になりますか。
② 平成30年に契約を更新し更新料を受け取り、その後平成31年に借主が変更となり、名義書換料を受け取った場合には、更新料・名義書換料とも臨時所得として平均課税を適用できるのでしょうか。
《質問事項》
当社(内国法人)の取締役であるAは、この度の人事異動により3年間の予定で米国の子会社の社長に就任しました。なお、子会社の社長に就任後も当社の取締役を兼務しており、当社と子会社の双方から役員報酬を受けています。
上記のような場合、当社と子会社の双方から受ける役員報酬はどのように処理すればいいのでしょうか。
《前提》
リビングニーズ特約で2つの保険会社から保険金を受け取りました。
A:被相続人平成29年10月死亡
B:相続人(被保険者の二男)
C:被相続人の孫(Bの長女小学生)
1. 日本生命
保険契約者 A
被保険者 A
保険受取人 B
6月にリビングニーズ特約によりBが保険金1,000万円を取得
約款には、保険金受取人、死亡保険金もリビングニーズ特約も受取人は同じと記載されている。
Bが保険金の受取人であることは間違いがない。
2. 三井生命
保険契約者 C(Aが毎年保険料相当分を孫へ贈与、贈与税申告済)
被保険者 A
保険受取人 C
6月にリビングニーズ特約によりBが代理人として保険金2,000万円を取得
約款には、リビングニーズ特約の受取人の記載がない。
三井生命に問い合わせても、「残ったお金を相続税で申告してください」としか言われない。
《質問事項》
当社(内国法人)では、米国の著名な経済学者であるA博士(米国のB大学教授)に日本国内での講演を依頼し、講演料を支払うことになりました。
A博士は、B大学とは関係なく個人の資格で来日するものですが、当社がA博士に講演料を支払う場合には、所得税(20.42 %)を源泉徴収することになるのでしょうか。
なお、A博士は、日本に恒久的施設(PE)を有していません。
《質問》
平成30年3月に個人事業を開始し、これまで5年6月(平成24年10月取得)にわたり家事用で使用していた車両を事業用に使うことにしました。平成30年分以降の減価償却費等はどのように算出するのかご教示ください。なお、車両の取得価額は500万円でした。
《前提》
・土地A、建物B・C・Dはすべて被相続人が所有
・建物B・C・Dを同族会社へ賃貸している
・賃貸借契約書には建物B・C・Dまとめて賃貸すると記載がある
・同族会社は建物B・C・Dをそれぞれ第三者へ賃貸している
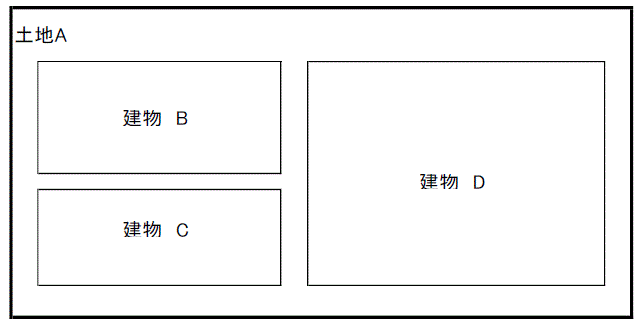
《質問》
上記前提において、土地A全体を一団の土地として評価して問題ないでしょうか?
(一団の土地とすると地積規模大が適用できるため、何とか一団の土地としたいです。)