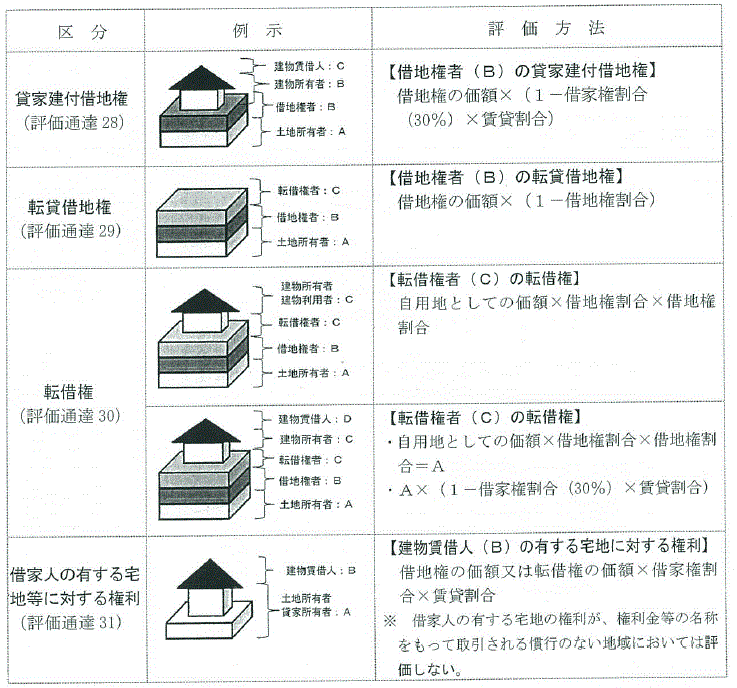《質問》
3月決算法人です。
当社の給与の支給は当月分を翌月15日に支払っております。(役員報酬も同じ)
今年の1月月初に臨時株主総会を開いて役員に就任した従業員Aについて従業員の期間は40万円の給料で、役員報酬は50万円としました。
この場合、1月分(2月15日支給)から役員報酬として50万円を支給する形で問題ないでしょうか。
「さくら税研フォーラム」は会員制の税務・会計情報サービスです。法人課税・個人課税・資産課税・消費税等税務全般に渡るポイント、毎年の税制改正の動向など、最新の税務情報を詳しく解説しています。
《質問》
3月決算法人です。
当社の給与の支給は当月分を翌月15日に支払っております。(役員報酬も同じ)
今年の1月月初に臨時株主総会を開いて役員に就任した従業員Aについて従業員の期間は40万円の給料で、役員報酬は50万円としました。
この場合、1月分(2月15日支給)から役員報酬として50万円を支給する形で問題ないでしょうか。
《質問》
被相続人の遺言によって、被相続人が居住していた自宅(土地・建物)を任意団体であるあしなが育英会(人格のない社団)に遺贈することとなりました。任意団体は租税特別措置法40条の対象外のため、法定相続人が準確定申告によりみなし譲渡所得税の申告をしなければならないと理解しています。このような遺贈のケースにおいても租税特別措置法35条の居住用不動産を売却した場合の3,000万円控除が適用可能でしょうか。
《質問》
私(個人)は、空き家となっているマンションをいわゆる民泊として利用しようと考えて所定の手続きを行いました。今後民泊で生じた所得等について課税関係はどのようになるかご教示願います。
《質問》
現在、法人でゴルフ会員権を所有しています。
活用しているのですが、そのゴルフ会員権におけるゴルフ場は、過年度において倒産して預託金の切り捨てという事態になったものでした。
その時点では、預託金の切り捨て損金処理をしないまま、購入時における取得価格で損益計算書に計上されたままになっております。
このゴルフ会員権を売却すると売却価格と簿価との差額が売却損して損金になるということで宜しいのでしょうか。
《質問》
平成30年1月1日に被相続人Aが亡くなりました。同居親族である子の相続人Bが被相続人Aの居住用の土地500㎡と建物を相続しました。その後、その土地の一部の30㎡を他の土地と合わせて平成30年5月1日に売却、引き渡しを行いました。
小規模宅地の特例(特定居住用宅地)の適用を受けるにあたりまして、相続人Bは居住継続要件は満たしていますが、上記売却したことにと伴い、保有継続要件は満たさないことになるのでしょうか。
《質問》
相続税の申告期限内に、小規模宅地の特例(特定居住用宅地等330㎡限度面積いっぱい)を受けて申告した後に、相続税の調査があってその特例の適用が否認された場合の件です。
上記の件で、申告期限後に修正申告を提出するにあたり、他の土地に振り替えて小規模宅地の特例(貸付事業用宅地等200㎡限度面積いっぱい)を受けることは可能でしょうか。
《質問》
当社は、インドネシアの法人から特許権の使用料の支払いを受けました。
我が国とインドネシア共和国との租税条約の規定では、特許権の使用料の支払いに係る限度税率は10%ととなっています。
ところが、今回、当社が支払いを受けた特許権の使用料に係る源泉徴収税率は20%となっていました。
インドネシアの国内法では、非居住者等に対して特許権の使用料の支払いをする場合の源泉徴収税率は20%とされていることから、国内法の規定に基づき20%の税率により源泉徴収をしたとのことです。
このような場合、外国税額控除の適用関係において、租税条約に定める限度税率10%を超えて源泉徴収された外国法人税の額はどのように取り扱われるのでしょうか。
《質問》
子会社
現金 100 / 買掛金 100
売掛金 100 / 資本金 50
/ 剰余金 50
(別途積立金 45、繰越利益金 5)
この法人を吸収した時の親会社の会計処理について教えてください。
親会社の子会社株式は60です。
資産、及び負債はそのまま受入処理をすればよいと考えますが、子会社の資本金、及び剰余金をどうするのか、子会社株式をどのように償却するのか合併法人(親会社)の会計処理及び税務処理についてお教えください。
【土地等の評価】《第6回》
Ⅷ 農地の評価
(1)農地の分類及び評価方法等(評価通達34ほか)
農地の分類(評価通達34)及び評価方法等は、次表のとおりです。
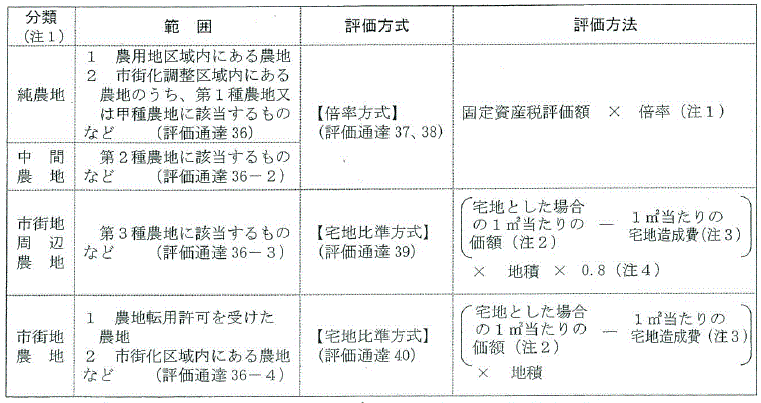
(注1) 評価倍率表の「田」、「畑」欄に、その地域の田・畑を評価する場合における農地の分類、評価方式及び固定資産税評価額に乗ずる倍率が記載されています。なお、農地の分類等は、次に掲げる略称を用いて記載しています。
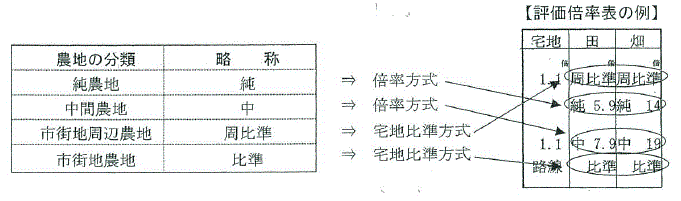
(注2) 「宅地とした場合の1㎡当たりの価額」は、その付近にある宅地について、評価通達11((評価の方式))に定める方式によって評価した1㎡当たりの価額を基とし、その宅地とその農地との位置、形状等の条件の差を考慮して評価することとされています(評価通達40注書参照)。
したがって、「宅地とした場合の1㎡当たりの価額」は、次表のとおりとなります。
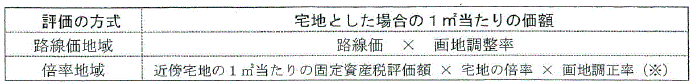
※普通住宅地区の画地調整率を参考とすることができます。
(注3) 農地を宅地比準方式で評価する場合の「宅地造成費」の金額は、財産評価基準書に掲載されています。
(注4 )市街地周辺農地については、「市街地農地であるとした場合の価額の80%相当額で評価する」(評価通達39)こととなっていますが、これは、宅地転用が許可される地域の農地ではあるが、まだ現実に許可を受けていないことを考慮したものです。
(参考)農地の評価上の分類と法令等との関係
農地は、農地法及び都市計画法等との関係によって、次の「評価上の分類」のいずれかに分類して評価します。
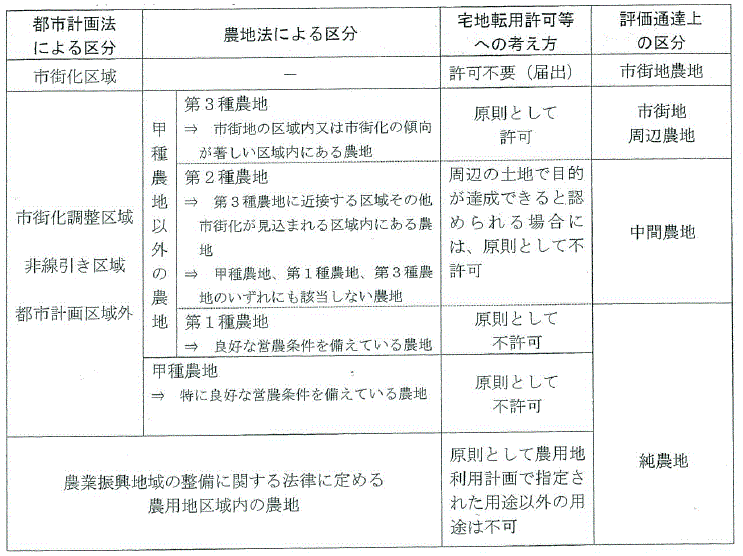
○質疑応答事例【農地の評価上の分類】
【市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差】
【地積規模の大きな宅地の評価市街地農地等】
(2)生産緑地の評価(評価通達40-3)
生産緑地法第2条第3号に規定する生産緑地(注)は、生産緑地としての利用上の制限を踏まえ、次の算式により評価します。
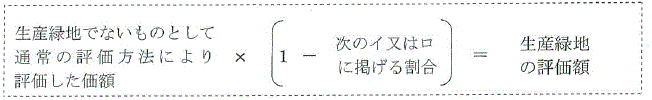
イ 課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
| 課税時期から買取り申出をすることができることとなる日までの期間 | 割 合 |
| 5年以下のもの | 100分の10 |
| 5年を超え10年以下のもの | 100分の15 |
| 10年を超え15年以下のもの | 100分の20 |
| 15年を超え20年以下のもの | 100分の25 |
| 20年を超え25年以下のもの | 100分の30 |
| 25年を超え30年以下のもの | 100分の35 |
※生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡した場合は、生産緑地でないものとして評価した価額の95%で評価します。
ロ 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地
100分の5
(注)課税時期において生産緑地法第10条の規定により、市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出(以下「買取りの申出」といいます。)を行った目から起算して3か月(生産緑地法の一部を改正する法律附則第2条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する旧第二種生産緑地地区に係る旧生産緑地にあっては1か月)を経過しているもの以外のものをいいます。
生産緑地に係る行為制限と「買取りの申出」 市街化区域内にある農地等のうち、公害又は災害の防止等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する上地として適しているものについては、その農地等の所有権者等の同意を得て、都市計則法及び生産緑地法の規定に基づき生産緑地地区に指定されます。 市街化区域内にある農地等が生産緑地地区に指定されると、その地区内にある農地等(生産緑地)について建築物の新築、宅地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならないこととされています(生産緑地法8)。更にこの許可は、農産物の生産集荷施設や市民農園に係る施設等を設置する場合以外は、原則として許可が下りないこととされている(生産緑地法8②)ことから、生産緑地地区に指定されると農地等以外の使用は原則的にできなくなります。 また、生産緑地法には「買取りの申出」制度が設けられていて、①生産緑地に係る指定の告示の日から起算して30年を経過したとき、又は②告示後に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができます(生産緑地法10)。 これにより買取りの申出を行った生産緑地については、買取りの申出の日から起算して3か月以内にその生産緑地の所有権が移転しない場合には、生産緑地法第8条に基づく行為の制限は解除されることになっています(生産緑地法14)。
(3)貸し付けられている農地の評価(評価通達41)
イ 耕作権の目的となっている農地の評価額(評価通達41 (1))
「耕作権の目的となっている農地」は、次の算式により評価します。

(注)「耕作権割合」は、財産評価基準書に掲載されています。
○質疑応答事例【農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価】
ロ 永小作権の目的となっている農地の評価額(評価通達41(2))
「永小作権の目的となっている農地」は、次の算式により評価します。
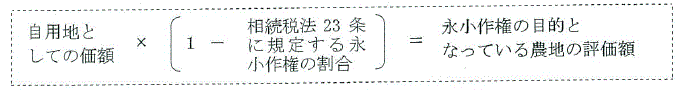
ハ 区分地上権の目的となっている農地の評価額(評価通達41 (3))
「区分地上権の目的となっている農地」は、次の算式により評価します。
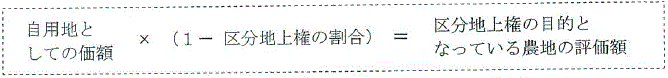
(注)区分地上権の評価及びその割合は、評価通達27-4を準用します。
ニ 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている農地の評価額(評価通達41(4))
「区分地上権に準ずる地上権の目的となっている農地」は、次の算式により評価します。
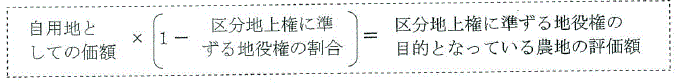
(注)区分地上権に準ずる地役権の評価及びその割合は、評価通達27-5 を準用します。
IX 山林・原野の評価
(1)山林の分類(評価通達45)及び評価方法等は、次表のとおりです。
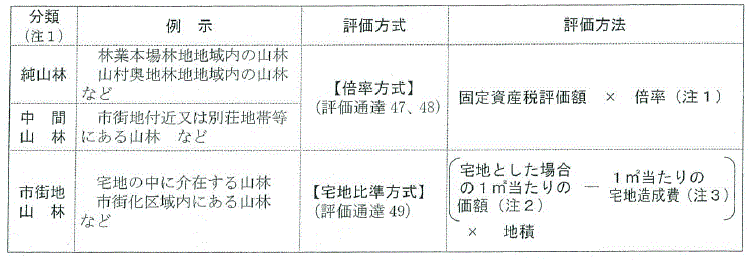
(注1) 評価倍率表の「山林」欄に、その地域の山林を評価する場合における山林の分類、評価方式及び固定資産税評価額に乗ずる倍率が記載されています。なお、山林の分類等は、農地の場合と同様に、次に掲げる略称を用いて記載しています。
| 山林の分類 | 略 称 | |
| 純山林 | 純 | ⇒ 倍率方式 |
| 中間山林 | 中 | ⇒ 倍率方式 |
| 市街地山林 | 比準 | ⇒ 宅地比準方式 |
(注2・3) 「宅地とした場合の1㎡当たりの価額」及び「宅地造成費」は、市街地農地の場合と同様です。
市街地山林を「近隣の純山林の価額に比準」して評価する場合 市街地山林であっても、①宅地比準方式で評価した場合の価額が近隣の純山林の価額を下回る場合、②その山林が急傾斜地であるため宅地造成ができないと認められる場合には、その市街地山林の価額は宅地比準方式ではなく、近隣の純山林の価額に比準して評価します(評価通達49なお書)。
(2)保安林等の評価(評価通達50、123)
森林法その他の法令の規定に基づき、土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林(以下「保安林等」といいます。)は、次の算式により評価します。
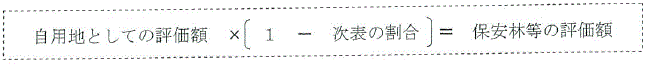
| 法令に基づき定められた伐採関係の区分(注) | 割 合 |
| 一部皆伐 | 0.3 |
| 択伐 | 0.5 |
| 単木選伐 | 0.7 |
| 禁伐 | 0.8 |
(注)「法令に基づき定められた伐採関係の区分」は、財産評価基準書の3. 参考「伐採制限等を受けている山林の評価」の「別紙 森林法その他の法令の範囲等」を参照してください。
公益的機能別施業森林区域内の山林及び立木の評価(個別通達) 公益的機能別施業森林区域内の山林及び立木の評価については、 ① 平成24年3日月31日以前に認定を受けた森林施業計画に係るもの(平成14年6月4日付課評2-3ほか1課共同) ② 平成24年4月1日以後に認定を受けた森林経営計画に係るもの(平成24年7月12日付課評2-35外一部改正)があります。
(3)特別緑地保全地区内にある山林の評価(評価通達50-2)
都市緑地法第12条に規定する特別緑地保全地区は、都市緑地法により都市における緑地を保全するために設けられるもので、特別緑地保全地区内にある山林等は、緑地としてしか利用することができないという厳しい制限があります。
このため、特別緑地儼全地区内にある山林は、次の算式により評価します。
自用地としての評価 × ( 1 - 0.8 ) = 特別緑地保全地区内にある山林の評価額
(4)貸し付けられている山林の評価(評価通達51)
イ 賃借権の目的となっている山林の評価額(評価通達51 (1 ))
「賃借権の目的となっている山林」は、次の算式により評価します。
自用地としての価格 - 賃借権の価格(注) = 賃借権の目的となっている山林の評価
(注)「賃借権の価額」は、次表のとおりです(評価通達54)。
| 山林の区分 | 賃借権の評価方法 |
| 純山林 | 賃借権の残存期間に応じ、相続税法23条に準じて評価(評価通達54 (1)) |
| 中間山林 | 賃貸借契約の内容等に応じ、「純山林の賃借権」又は「市街地山林の賃借権」により求めた価額によって評価(評価通達54 (2)) |
| 市街地山林 | その山林の付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた価額によって評価(評価通達54 (3)) |
ロ 地上権の目的となっている山林の評価額(評価通達51 (2))
「地上権の目的となっている山林」は、次の算式により評価します。
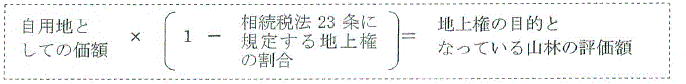
ハ 区分地上権の目的となっている山林の評価額(評価通達51 (3))
「区分地上権の目的となっている山林」は、次の算式により評価します。
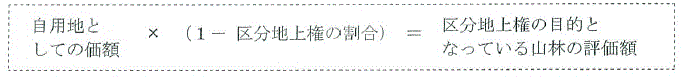
(注)区分地上権の評価及びその割合は、評価通達27-4を準用します。
ニ 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている山林の評価額(評価通達51(4))
「区分地上権に準ずる地上権の目的となっている山林」は、次の算式により評価します。
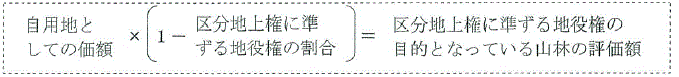
(注)区分地上権に準ずる地役権の評価及びその割合は、評価通達27-5を準用します。
(5)原野の評価(評価通達57ほか)
原野は、山林と同様に評価します(評価通達57ほか)。
Ⅹ 鉱泉地等の評価
鉱泉地等の評価方法(概要)は、次表のとおりです。
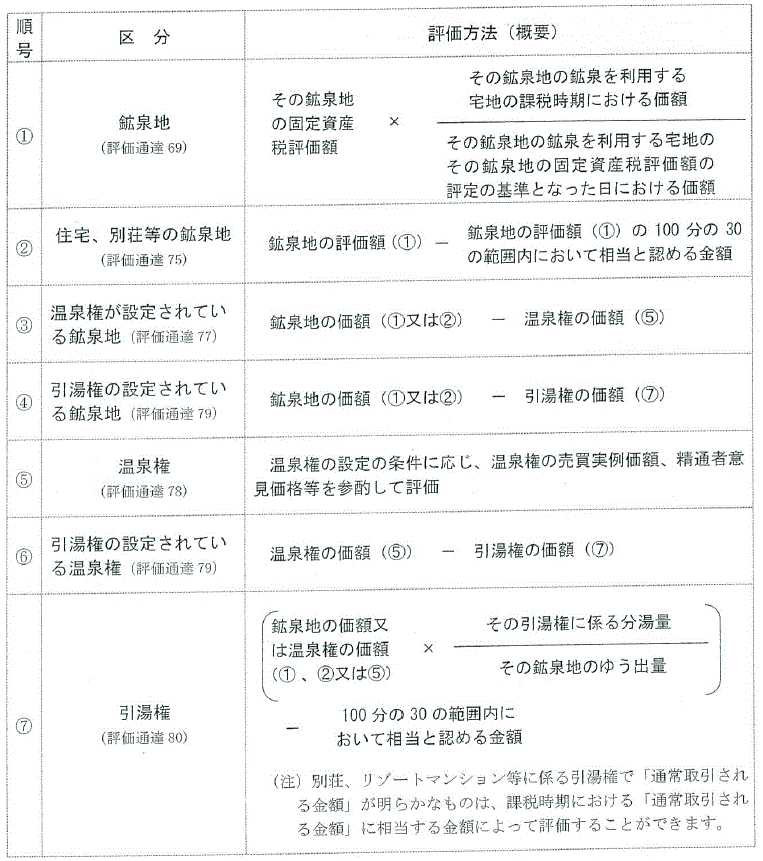
Ⅺ 雑種地の評価
(1)雑種地の評価方法に関する基本的な考え方(評価通達82)
雑種地とは、宅地から原野までの地目のいずれにも該当しない土地であり、例え
ば、遊園地、運動場、ゴルフ場、競馬場、飛行場、テニスコート、鉄塔敷地、鉄軌道用地などがあります。
このような雑種地の原則的評価方式は、近傍にある状況が類似する土地の評価額に比準する方式(農地比準、山林比準、宅地比準など)であることを定めています。
この場合、評価対象地である雑種地と状況が類似する(比準する)付近の土地(地目)の判定に当たっては、評価対象地の付近の状況を十分考慮して判定する必要があります。
(注)ゴルフ場用地、遊園地等用地、文化財建造物である構築物の敷地及び鉄軌道用地については、別途、評価通達でその評価方法が定められています(評価通達83、83-2 、83- 3及び84)。
(2)市街化調整区域内にある雑種地の評価
○質疑応答事例【市街化調整区域内にある雑種地の評価】
【参考】都市計画法第34条(抜粋)
第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為~(中略)~については、~(中略)~、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。 ― 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(いわゆる「集落サービス店舗の敷地」に係る開発行為) 二~八 (略) 九 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為(いわゆる「ドライブイン等の沿道サービス施設の敷地」に係る開発行為) 十 (略) 十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの(いわゆる「条例指定区域内の土地」に係る開発行為) 十二~十四 (略)
(3)貸し付けられている雑種地の評価(評価通達86ほか)
イ 賃借権の目的となっている雑種地の評価額(評価通達86(1))
「賃借権の目的となっている雑種地」は、次の算式により評価します。
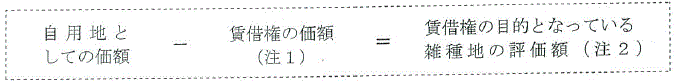
(注1)「雑種地に係る賃借権の価額」は、原則として、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して評価しますが、次表に掲げる区分にしたがって、評価することができます(評価通達87)。
| 賃借権の区分 | 賃借権の価額 |
| 地上権に準ずる賃借権(※) | 雑種地の自用地としての価額に、①賃借権の残存期間に応じ、その賃借権が地上権であるとした場合に適用される相続税法第23条に規定する割合(以下「法定地上権割合」といいます。)又は②その賃借権が借地権であるとした場合に適用される借地権割合のいずれか低い割合を乗じた価額(評価通達87 ( 1 )) |
| 上記以外の賃借権 | 雑種地の自用地としての価額に、賃借権の残存期間に応じ、その賃借権が地上権であるとした場合に適用される法定地上権割合の2分の1の割合を乗じた価額(評価通達87 (2)) |
※ 例えば、①賃借権の登記がされているもの、②設定の対価として権利金その他の一時金の授受のあるもの、③堅固な構築物の所有を目的とするものなどです
(注2)(注1)によって評価した賃借権の価額が次表に掲げる金額を下回る場合には、その雜種地の自用地としての価額から次表に掲げる金額を控除した金額によって評価します(評価通達86 (1)ただし書)。
| 賃借権の区分 | 金 額 |
| 地上権に準ずる賃借権 | 1 その雑種地の自用地としての価額に、その毀借権の残存期間に応じた次に掲げる割合を乗じた金額 (1)残存期間が5年以下100分の5 (2)残存期問が5年超10年以下100分の10 (3)残存期間が10年超15年以下100分の15 (4)残存期間が15年超100分の20 |
| 上記以外の賃借権 | 2 その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じ上記1に掲げる割合の2分の1の割合を乗じた金額 |
賃借人が雑種地の造成を行っている場合の評価方法(評価通達86(注)書) 通常、ゴルフ場用地は、賃借人がゴルフ場としての造成工事を行っていますが、その場合には、「造成が行われていないものとした場合のその雑種地の自用地としての価額」から「賃借権の価額」を控除して評価します。
ロ 権の目的となっている雑種地の評価額(評価通達86 (2))
「地上権の目的となっている雑種地」は、次の算式により評価します。
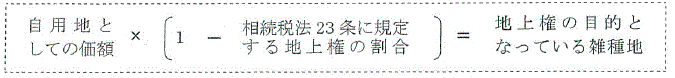
ハ 区分地上権の目的となっている雑種地の評価額(評価通達86 (3))
「区分地上権の目的となっている雑種地」は、次の算式により評価します。
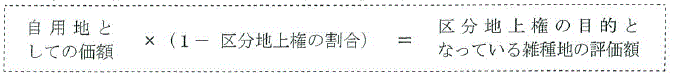
(注)区分地上権の評価及びその割合は、評価通達27-4を準用します。
ニ 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている雑種地の評価額(評価通達86(4))
「区分地上権に準ずる地上権の目的となっている雑種地」は、次の算式により評価します。
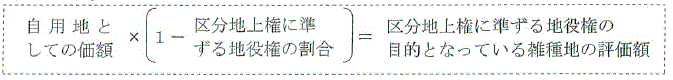
(注)区分地上権に準ずる地役権の評価及びその割合は、評価通達27-5を準用します。
【土地等の評価】《第5回》
Ⅴ 貸宅地の評価
借地権等が設定されている宅地(貸宅地)については、これらの権利の価額に相当する減価が生じていると考えられることから、評価通達では、貸宅地の評価に当たっては、その宅地の自用地としての価額から設定されている権利の価額を控除して評価することとしています。
(1)普通借地権の目的となっている宅地の評価(評価通達25(1))
「普通借地権の目的となっている宅地」は、次の算式により評価します。
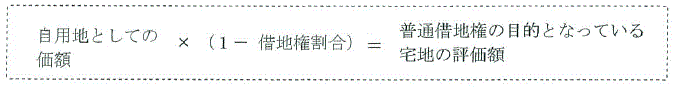
相当の地代を収受している貸宅地の評価等(個別通達)
土地を同族会社に賃貸する場合等において普通借地権の設定に当たり権利金の授受に代えて相当な地代を支払うことが約定されるなど特殊な場合の評価方法等については、以下の個別通達があります。
○ 相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和42年12月5日)
○ 相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて(昭和60年6月5日)
○質疑応答事例【複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価】
(2)定期借地権の目的となっている宅地の評価(評価通達25 (2))
「定期借地権の目的となっている宅地」は、次の算式により評価します。
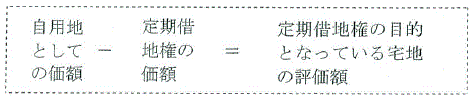
一般定期借地権の目的となっている宅地の評価(簡便法)
借地借家法第22条に規定する「一般定期借地権」の目的となっている宅地については、次の個別通達により、課税上弊害がない限り、評価通達による原則評価に代えて、「底地割合」を基として評価することとしています。
○一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて(平成10年8月25日)
○質疑応答事例【一般定期借地権の目的となっている宅地の評価一簡便法(1)】
【一般定期借地権の目的となっている宅地の評価一簡便法(2)】
(3)地上権の目的となっている宅地の評価(評価通達25 (3))
「地上権の目的となっている宅地」(注)は、次の算式により評価します。
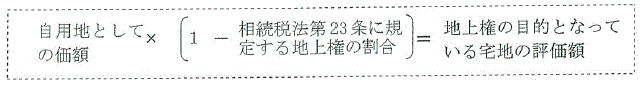
(注)建物所有を目的とする地上権の目的となっている宅地は、上記1の「普通借地権の目的となっている貸宅地」又は上記2の「定期借地権の目的となっている貸宅地」として評価することになります。
(4)区分地上権の目的となっている宅地の評価(評価通達25 (4))
「区分地上権の目的となっている宅地」は、次の算式により評価します。
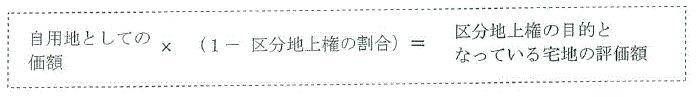
○質疑応答事例【区分地上権の目的となっている宅地の評価】
(5)区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価(評価通達25 (5))
「区分地上権に準ずる地上権の目的となっている宅地」は、次の算式により評価します。
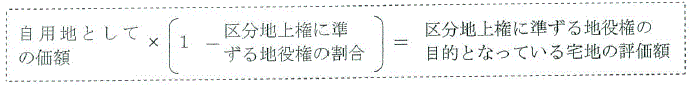
○質疑応答事例【区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価】
Ⅵ 借地権等の評価
評価通達9に定める土地の上に存する権利のうち、宅地の上に存する権利としては、①普通借地権、②定期借地権、③地上権、④区分地上権及び⑤区分地上権に準ずる地役権の5種類があり、これらの権利の評価方法について説明します。
(1)普通借地権の評価(評価通達27)
「普通借地権」(注1)は、次の算式により評価します。
自用地としての価額 × 借地権割合(注2) = 普通借地権の評価額
(注)1 借地借家法(平成3年法律第90号)の制定(平成4年8月1日施行)により認められた一般の借地権(借地借家法第2条)は、「普通借地権」といわれています。また、借地借家法の施行前に成立している既存の借地権については、従前の取扱いが適用されます(同法附則第4条ただし書)。
評価通達では、これら2種類の借地権をいずれも建物の所有を目的とする地上権又は賃借権である「借地権」として取り扱っています。
2 借地権割合は、路線価地域においては路線価図でAからGまでの記号により、倍率地域においては評価倍率表でパーセントにより表示されています。
(2)定期借地権の評価(評価通達27-2)
定期借地権制度は、その種類と設定期間との組み合わせにより多種多様な借地契約の設定が想定され、借地契約の内容も、地代額の設定から権利金・保証金の支払いの有無(多寡)にいたるまで、極めて個別性が強く、また、借地契約の更新がなく契約終了により確定的に借地関係が終了することから、借地契約の残存期間の長短によって定期借地権の価額は異なることになります。
上記を踏まえ、評価通達では簡便法として、「定期借地権設定時において借地人に帰属する経済的利益の総額」を基に、「課税時期における残存期間」を考慮して、次の算式により定期借地権の価額を算定します。
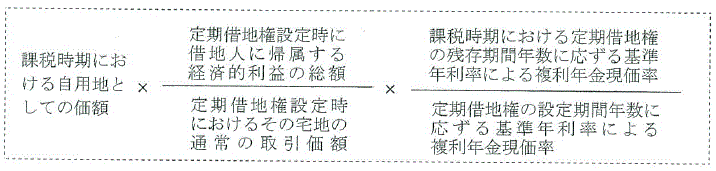
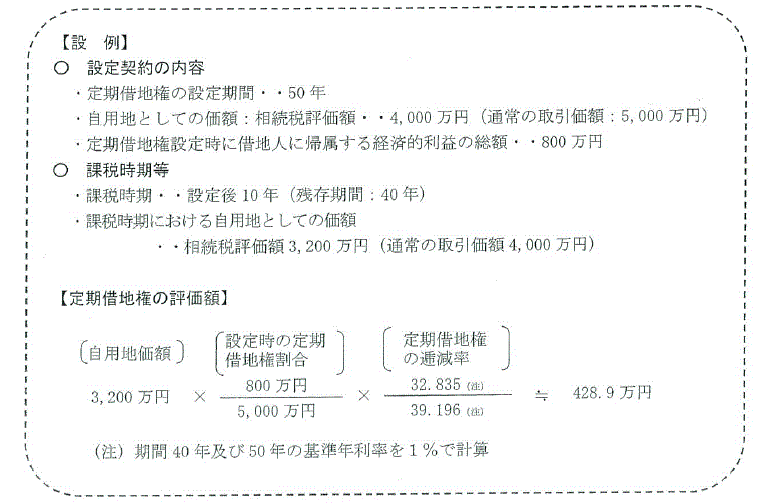
「定期借地権設定時に借地人に帰属する経済的利益の総額」の求め方
定期借地権設定時に借地人に帰属する経済的利益には、①借地契約終了の時に返還を要しない権利金などの一時金の支払いに伴う前払地代、②借地契約終了の時に返還を必要とするが、無利息又は低利で預託される保証金に伴う前払地代、③地代が低額で設定されたことに伴う差額地代があります。
なお、具体的な計算方法は、評価通達27-3 に定められています。
「基準年利率」及び「複利年金現価率」
各年月の基準年利率及び各利率に係る複利年金現価率等については、国税庁ホームページの法令解釈通達(財産評価関係:個別通達)の「平成○年分の基準年利率について」で公表されています。
(3)地上権の評価(相続税法23)
「地上権」(注)は、次の算式により評価します。
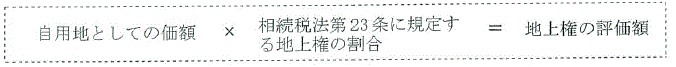
(注)地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するためにその土地を使用する権利(民法第265条)をいいますが、建物所有を目的とする地上権は「借地権」に該当しますので、上記1の「普通借地権」又は上記2の「定期借地権」として評価することになります。
(4)区分地上権の評価(評価通達27-4)
民法269条の2の規定による地上権は、工作物の所有を目的とし、土地の一定層を客体として設定されるものであり、「区分地上権」と呼ばれています。
この区分地上権は、通常、鉄道や道路のためのトンネルの所有を目的とするものが多く、この場合には、国土交通省が中心となって設けている中央用地対策連絡協議会理事会が定めた「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」に定める「土地利用制限率算定要領」を基として補償金が支払われているのが現状です。
このような現状を踏まえ、区分地上権は、次の算式により評価します。
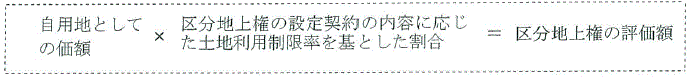
なお、設定事例が最も多い地下鉄等のトンネルの所有を目的とする場合の区分地上権の割合は、過去の補償金の支払事例等から、30%とすることができます。
【地下鉄等のトンネルの所有を目的とする区分地上権の評価(簡便法)】
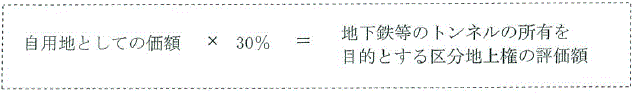
(5)区分地上権に準ずる地役権の評価(評価通達27-5)
「区分地上権に準ずる地役権」とは、特別高圧架空電線の架設等を目的として、地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、建造物の設置を制限するものとされています(地価税法施行令第2条第1項)。
このような地役権は、区分地上権と同じ内容(効果)をもつものであり、地役権設定に当たり支払われる保証金も、区分地上権の場合と同様に、「土地利用制限率算定要領」を基として補償金が支払われているのが実情です。
このため、「区分地上権に準ずる地役権」は、区分地上権と同様に、次の算式により評価します。
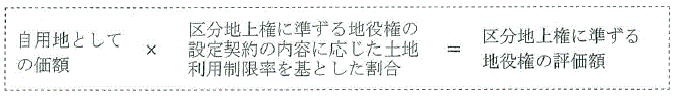
なお、「区分地上権に準ずる地役権」は、建造物の設置を制限するものであることから、家屋に対する建築制限の強弱に着目し、①家屋の建築が全くできない場合には50%又は借地権割合のいずれか高い割合を、②家屋の建築ができるとしても、その構造、用途等に制限を受ける場合には30%の割合を、基にして評価することができます。
特別高圧架空電線
区分地上権に準ずる地役権が存する土地 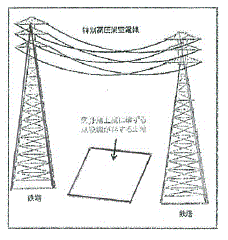
鉄塔 鉄塔
【「区分地上権に準ずる地役権」の評価(簡便法)】
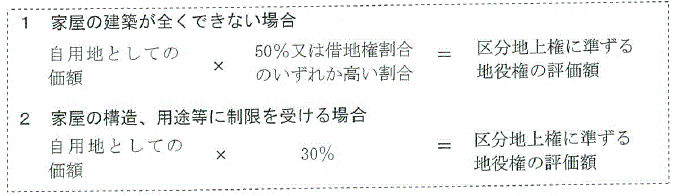
Ⅶ 貸家建付地等の評価
(1)貸家建付地の評価(評価通達26)
貸家の借家人は家屋に対する権利を有するほか、その家屋の敷地(貸家建付地)についても、家屋の賃借権に基づいて、家屋の利用の範囲内で、ある程度の支配権を有していると認められ、逆にその範囲において、地主(貸家建付地の所有者)は、利用についての受忍義務を負うこととなります。
そのため、借家人の有する支配権を消滅させるためには、いわゆる立退料の支払いを要する場合もあり、また、その支配権が付着したままの状態でその土地(貸家建付地)を譲渡するとした場合には、支配権が付着していないとした場合における価額より低い価額でしか譲渡できない場合もあります。
そこで、貸家建付地の価額は、自用地としての価額から借地権割合と借家権割合(30%)の相乗積を乗じて計算した価額を控除した価額によって評価することとしています。
また、アパートや貸ビルの一部に賃貸の用に供されていない部分がある場合には、上記の考え方に基づき、課税時期において現実に貸し付けられている部分の割合を賃貸割合と定め、次の算式により、貸家建付地の評価額を求めることとしています。
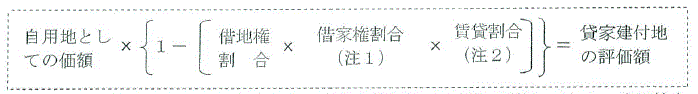
(注)1 借家権割合は、評価倍率表の「借家権割合」の欄に記載してあり、当局管内6県の借家権割合は、全て30%です。
2 賃貸アパートなど、その貸家に係る各独立部分がある場合の賃貸割合は、次の算式により計算します。
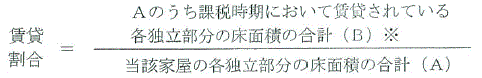
※ 賃貸割合の算定に当たって、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められる各独立部分」がある場合には、その各独立部分の床面積を、賃貸されている各独立部分の床面積(B)に加えて賃貸割合を計算して差し支えありません。
なお、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められる」かどうかは、その部分が
① 各独立部分か課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか、
② 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか、
③ 空室の期間、他の用途に供されていないかどうか、
④ 空室の期間が課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であったかどうか、
⑤ 課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか、
などの事実関係から総合的に判断します。
○質疑応答事例【貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価】
【貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲】
(2)貸家建付借地権等の評価(評価通達28~31)