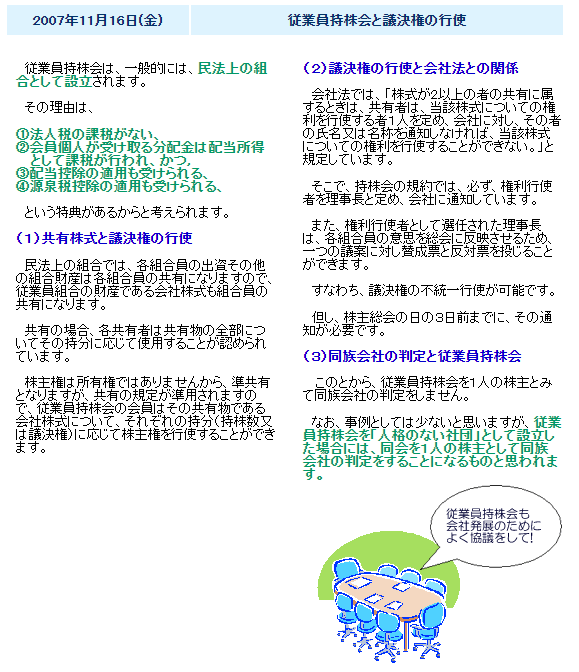《前提》
普通株式とA種類株式(内容は配当優先&議決権なし)を発行している会社があります。
・発行済株式数15,000株
<内訳>
・代表取締役社長 普通株式1,000株
・社長の子(取締役営業部長に就任予定) A種類株式1,000株
・従業員持株会(民法上の組合方式で構成員は赤の他人で5名)
A種類株式13,000株 (2,600株×5人=13,000株)
① 同族会社の判定1
1. 持ち株で判定
民法上の組合形式の持株会は構成員5名の合計株数を1人の株主グループとするのか、各構成員を1グループとするのかどちらでしょうか。
次頁資料を見ると議決権の不統一行使が可能なので単独で判定するとあります。
単独判定だとすると持ち株会の上位3人×2,600 = 7,800 / 15,000 = 52%
50%超なので同族会社1人の株主と見ると、(第1グループ持株会13,000+第2グループ社長一族2,000) / 15,000=100%
50%超なので同族会社どちらが正しいでしょうか。
2. 議決権で判定1,000 / 1,000 = 100% 50%超なので同族会社
② 同族会社の判定2
私の理解ですと、持ち株判定と議決権判定のどちらか大きい方で判定するとの理解ですが合っていますか。
③ 社長の子の使用人兼務役員の判定について
上記判定2が正しいとすると、議決権割合で判定すると社長グループが100%になるので議決権で判定する ⇒ 同族会社 ⇒ 50%基準と10%基準は満たすが5%基準は満たさない(議決権がない)ので、使用人兼務役員になれるとの理解ですが合っていますか。
④ みなし役員の可能性
仮に社長の子がただの部長に就任した場合みなし役員とされる可能性はありますか。
⑤ 執行役員について
社長の子が、社内呼称及び名刺に常務執行役員と記載する(会社法の取締役ではないので登記はない)だけにした場合、役員ではないので、定期同額給与でなくてもOK&事前確定届も提出する必要ないので支払う賞与は損金算入OKだと考えますが正しいでしょうか。
〔木本税務会計事務所コラム〕
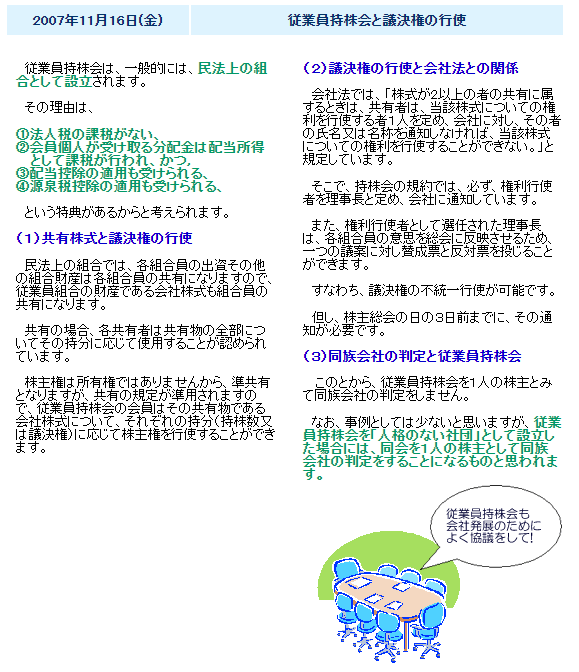
“種類株式がある場合の使用人兼務役員の判定など” の続きを読む