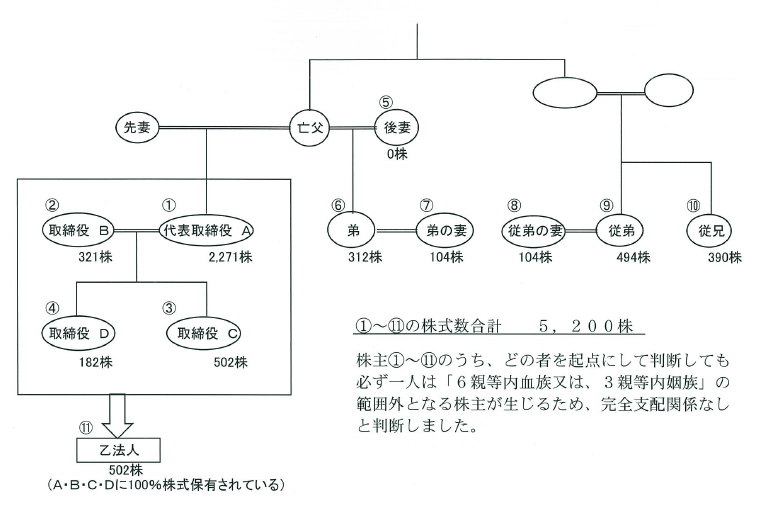【納税義務者】
チェック(1) 基準期間の課税売上高の判定
● 基準期間が免税事業者である場合:消基通1-4-5
● 基準期間中に事業用資産(賃貸用住宅)を譲渡した場合
⇒建物と土地等の一括譲渡のケース 消基通10-1-5
● 基準期間の中途で新たに事業を開始した場合:消基通1-4-9
※基準期間が1年でない法人(消法9②二)と相違する点に留意
● 輸出免税売上高:消基通1-4-2
● 非居住者が日本国内で商品販売を行う場合:消基通5-1-11
● 法人成り(法人に引き継いだ事業用資産の譲渡対価)
チェック(2) 相続があった場合の納税義務の免除の特例
● 相続があった年の前々年の課税売上高が1,000万円以下である相続人
が、課税事業者である被相続人の事業を承継したとき
①相続のあった年(消法10①)
②相続があった年の翌年と翌々年(消法10②)
● 被相続人が2以上の事業場を有していた場合で、2人以上の相続人が各
事業場ごとに分割して承継したとき(消法10③)
チェック(3) 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例
● 特定期間の中途で開業した場合の課税売上高(消法9の2④一)
※前年の1月1日から6月30日まで(個人事業者の特定期間)の
課税売上げで判定。参照:法人の特定期間(消法9の2④二、三)
● 特定期間中に支払った給与等支払額の範囲:消基通1-5-23
チェック(4) 高額特定資産を取得した場合納税義務の免除の特例(消法12の4)
● 平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れを行ったが、同年分の課
税売上高が1,000万円を超えなかった場合
● 平成28年4月1日以後に自己建設高額特定資産について、建設等に要し
た費用の額が税抜1,000万円以上となった日の属する課税期間の課税売
上高が1,000万円を超えなかった場合
【非課税取引】
チェック(1) 土地の貸付け
● 土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合:消基通6-1-4
● 土地の貸付期間の判定:同上
● 土地付建物等の貸付け: 消基通6-1-5
⇒ 更地のままの貸付け
⇒ 貸付け等に係る対価を建物分と土地分とに区分しているとき
チェック(2) 土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料:消基通6-1-6
チェック(3) 郵便切手類の譲渡
● 購入していた印紙を、金券ショップに売却した場合:消基通6-4-1
チェック(4) 物品切手等の発行
● 酒類小売店において、ビール券と引き換えにビールを販売した場合
:消基通6-4-5 同9-1-22
チェック(5) 住宅の貸付け関係
● 用途変更の場合の取扱い:消基通6-13-8
住宅以外の用途に変更することについて
⇒ 契約当事者間で契約変更をした場合
⇒ 契約変更なしに賃借人において事業の用に供した場合
チェック(6) 平成29年度改正事項
● 仮想通貨の譲渡に係る課税関係の見直し
⇒ 非課税とされる支払手段に類するものの範囲に、資金決済に
関する法律に規定する仮想通貨を加える(消令9④、48②一)
《適用関係》
平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては従前の例による(改正消令附則2)。
ただし、①施行日の前日に100万円以上(税抜き)の仮想通貨を有しており、かつ、②施行日前1月間の平均保有数量に比べ、施行日前日の保有数量が増加している場合には、当該増加分の課税仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除を認めない(改正消令附則8)。
【課税の対象】
チェック(1) 事業としての意義
● 事業規模に達していない建物(居住用は除く。)の賃貸収入
〈例〉建物一棟を業務用として反復、継続、独立して賃貸している場合
:消基通5-1-1
チェック(2) 付随行為:消基通5-1-7
● 事業用車両を売却(下取り)した場合
チェック(3) 自家消費等における対価:消基通10-1-18
● 棚卸資産を家事消費した場合
チェック(4) 法人成り
● 現物出資により事業用資産を法人に引き継いだ場合
:消法2①八、消令2①二、同令45②三
チェック(5) 借家保証金、権利金等:消基通5-4-3
● 賃貸借契約上賃貸借の終了時に返還される保証金等を受領した場合
チェック(6) 前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期:消基通9-1-27
● 所得税法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の適用を
受けない場合
<参照> 課税仕入れを行った日の意義(消基通11-3-1)
チェック(7) 自家消費等における対価:消基通10-1-1、同10-1-18
● 棚卸資産以外の事業用資産を家事消費した場合
【課税標準】
チェック(1) 課税資産の譲渡等の対価の額:消基通10-1-1
● 棚卸資産を通常より安い値段で他に販売(次の場合を除く)した場合
● 保有する棚卸資産又は事業用資産の家事消費又は家事使用した場合
チェック(2) 課税資産の譲渡等に際しての資産の下取り:消基通10-1-17
チェック(3) 委託販売等に係る手数料:消基通10-1-12
● 委託販売等における委託者と受託者それぞれに係る課税標準
チェック(4) 売上げに係る対価の返還等の処理:消基通14-1-8
【課税仕入れ】
チェック(1) 費途不明の交際費等:消基通11-2-23
● 接待交際費勘定中に、費途が明らかでないものや、贈答用に購入
した商品券及びビール券の購入代金が含まれている場合
チェック(2) 個人事業者と給与所得者の区分(消法2①十二)
● 課税仕入れに該当する(事業所得)か 否(給与所得)かの判定
<参考>
⇒ 消基通1-1-1に示された事項を総合勘案して判定
⇒ 課税当局の資料:「法人税課速報(源泉所得税関係)【給
与所得と事業所得との区分】東京国税局平成15年7月
第28号」・・・情報公開法9条1項による開示情報
チェック(3) 会費、組合費等:消基通5-5-3
⇒ 同業者団体、組合等に対して支払う通常会費
⇒ 会費名目で支払われる出版物の購読料、職員研修の受講料など
チェック(4) 家事共用資産の取得:消基通11-1-4
⇒ 当該資産の家事消費又は家事使用に係る部分の計算方法
⇒ 当該資産を一時的に家事使用した場合
<参照> 家事共用資産の譲渡(消基通10-1-19)
チェック(5) 従業員の通勤手当:消基通11-2-2
● 通勤に通常必要と認められる金額ではあるが、所得税法上の非課税
限度額を超えている場合
チェック(6) 課税仕入れ等に係る消費税額の控除(消法30②)
⇒ 当課税期間における課税売上割合及び課税売上高の把握
⇒ 当課税期間が1年に満たない場合
⇒ 課税売上割合の端数計算(処理):消基通11-5-6
チェック(7) 一括比例配分方式の2年以上の継続適用:消基通11-2-21
● 一括比例配分方式を採用した課税期間の翌課税期間の課税売上高が5億
円以下かつ課税売上割合が95%以上となった場合の「全額控除」
チェック(8) 更正の請求の可否(通則法23①)
● 一括比例配分方式を選択して確定申告した後の個別対応方式への変更
【控除対象仕入税額の調整】
チェック(1) 免税事業者が翌課税期間は課税事業者となる場合
● 棚卸資産に係る控除対象仕入税額の調整:消基通12-6-1
● 免税事業者時の課税売上げに係る翌課税期間中の値引・返品
チェック(2) 課税事業者が翌課税期間は免税事業者となる場合
● 棚卸資産に係る控除対象仕入税額の調整:消基通12-6-4
【簡易課税制度】
チェック(1) 簡易課税不適用届出書の提出時期
チェック(2) 固定資産等の売却収入の事業区分:消基通13-2-9
● 小売業を営む課税事業者が事業用固定資産を売却した場合
● みなし仕入率の計算の特例(75%ルール)の有無
チェック(3) 75%ルールの判定
● 酒類小売業及び卸売業を営む課税事業者のビール券売上げ
● 75%ルール判定時の端数処理
チェック(4) 食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い
● 精肉(鮮魚)の小売業(第2種)を営む課税事業者が焼鳥、ロースト
チキン(かつおのたたき、焼魚)等に加工販売している場合
:消基通13-2-2、同13-2-3
チェック(5) 小売店が販売したものの購入者が他の事業者であった場合(消令57⑥)
チェック(6) 塗装工事業の判定:消基通13-2-4
⇒ 塗料等の資材を自ら調達する事業形態
⇒ 他人が調達した塗料を塗装する(加工賃)だけの事業形態
チェック(7) 無償で譲り受けたものを事業者に販売している場合(消令57⑥)
チェック(8) 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義
● 農作業受託金(農業従事者が他の農業従事者の田植え、稲刈り等を
手伝い、得た収入金):消基通13-2-7
チェック(9) 簡易課税制度適用者の基準期間の課税売上高が6,000万円となった
場合
チェック(10) 相続があった場合の納税義務の免除の特例と簡易課税制度の適用
● 「簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者が、平成27年中に
相続により被相続人の事業を引き継いだ場合、基準期間(平成27年)
の相続人と被相続人の課税売上高の合計額が5,000万円超のとき(相
続人のみの課税売上高は5,000万円以下)の簡易課税制度適用の可否
チェック(11) 簡易課税制度選択届出書の効力:消基通13-1-3
● 簡易課税制度を適用している事業者が、免税事業者となった後、再び
課税事業者になった場合
【その他の誤りやすいポイント】
➣ 課税事業者が、免税事業者であった課税期間に発生した売掛金等につ
き貸倒れが生じたので、消費税額から控除している。
➣ 消費税の控除不足税額のある還付申告書が提出されたが、明細書の添
付がないにもかかわらず、消費税の還付を行っている。
➣ 課税期間の短縮(3か月)の適用を受けていた事業者が、平成29年1月
20日に不適用届出書を提出し、平成29年1月1日から原則的な課税期間
に戻すこととしている。
➣ 各年分の修正申告により納付すべきこととなった消費税を、その各年
分の所得の計算において租税公課に算入した。
➣ 小包郵便物でまとめて提出された「消費税課税事業者選択届出書」、
「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出日を通信日付によるとして
いる。