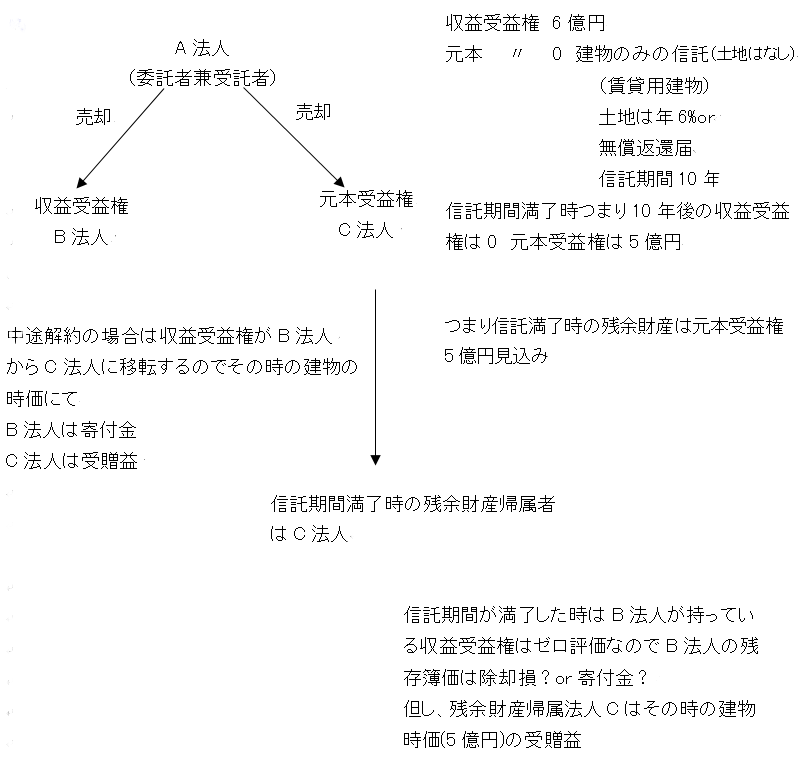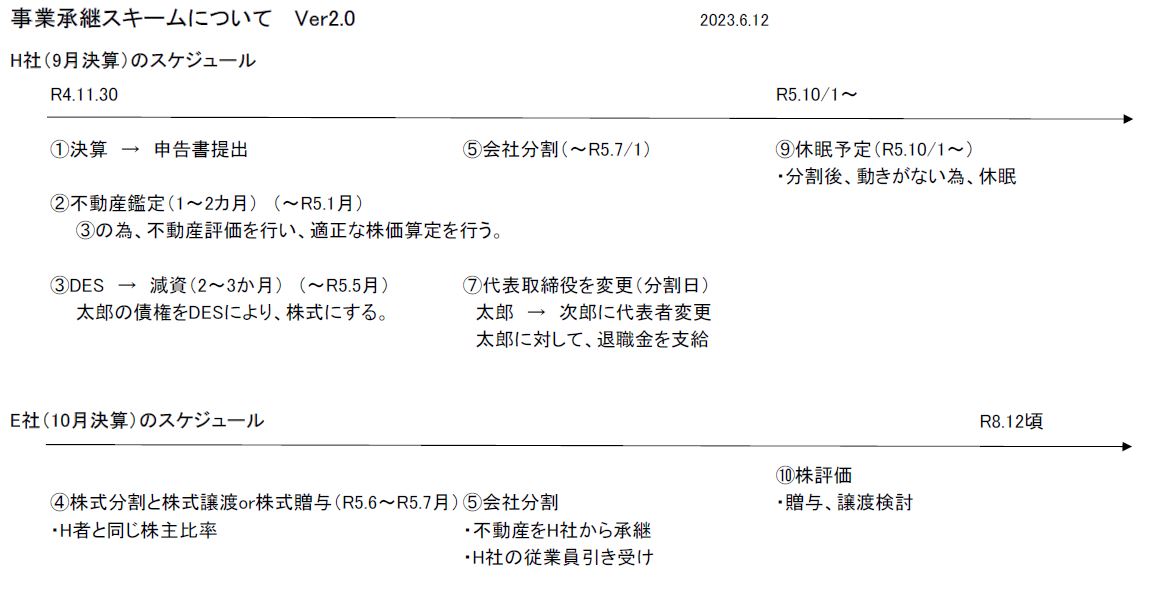《前提》
自己株式33,751,200円があります(資料参照)自己株式取得時の計算は
28,126株 × @1,200円 = 33,751,200
このたび、この自己株式すべてと従業員持ち株会の社員2名の持ち株すべてを現社長の父(既存株主で前代表取締役=創業者)が買い取る事になりました。背景にコロナで急速に業績悪化 ⇒ 従業員持ち株会の社員が譲渡を希望も買い手がいない ⇒ 仕方なく自己株式化 ⇒ さらなる業績悪化で銀行から自己株式の解消の要求&持ち株会の他の社員から更なる譲渡希望 ⇒ 買い取る資金のある人が創業者しかいないという流れになっています。
(1)自己株式の処分について
◇ この株式の買い取り単価(適正な時価)の算出方法を教えてください。
◇ この会社は財産評価通達の大会社に該当するかと思います(従業員116名、うちパートアルバイト11名)。類似業種比準価額で計算すると単価は@997円になります。時価が997円であるとした場合、課税関係は下線のとおりでよろしいでしょうか。
(会社の処理) 資本等取引につき課税関係の問題は生じない
(現金預金) 28,041,622 (自己株式) 33,751,200
(自己株式処分差損 = その他の資本剰余金) 5,709,578
(個人の処理) 発行会社が自社の株式を買い取った場合のみなし配当のような規定はないので課税関係なし
(投資有価証券)28,041,622 (現金預金)28,041,622 ←取得価格
◇ 時価より低い価格又は高い価格で譲渡した場合のそれぞれの課税関係を教えてください。
◇ 自己株式を処分した場合、その他の資本剰余金がなくマイナスになるので、別途積立金を減らすしかないと思いますが正しいでしょうか?
(2)従業員持ち株会の社員の株式を社長の父が買い取る場合について
持ち株会は民法上の組合方式です。持ち株会発足時の買取価格が1,200円で、以後持ち株会内での従業員同士での価格も1,200円で動かせないという事情があります。
◇ この株式の買い取り単価(適正な時価)の算出方法を教えてください。
◇ 時価より低い価格又は高い価格で譲渡した場合のそれぞれの課税関係を教えてください。
《資料》
同族会社等の判定に関する明細書