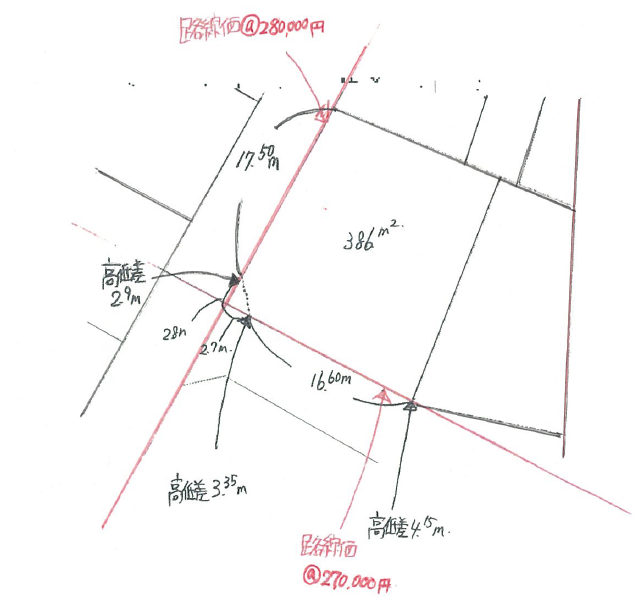《質問》
平成28年税制改正により住宅借入金等特別控除を非居住者でも受けられるようになりましたが、その手続きについての質問です。平成29年2月に住居を新築しましたが、その住居に住むことなく29年4月1日に2年間の予定で外国に勤務することになってしまいました。妻と子供は国内に留まり4月から新築した住まいに居住しています(住宅借入金等特別控除を受けるための他の要件は満たしています。)。
国税庁HPによると「海外に単身赴任等する場合(平成28年4月1日以後に住宅の取得等をして海外に単身赴任等することにより、非居住者となる者に限ります。)
平成28年4月1日以後に住宅の取得等をした方が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、海外に転出し、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、これらの親族が引き続き居住している当該住宅について住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、国内に納税管理人を定め、その納税管理人を通じて翌年に確定申告を行います。」と記載されています。
これは、本人が新居に居住していなくても、家族が住んでいる等条件を満たしていれば、平成29年3月までの国内での給与所得(年末調整済)について納税管理人を定めて確定申告(還付申告)をすればよいということなのでしょうか。また、納税管理人を定めずに日本に帰国後、期限後申告(還付申告)により住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできるのでしょうか。