《質問》
別添のパンフレットのような保険商品を関与先に提案する保険会社の担当者がおり特徴①、②、③等をセールスポイントとして売りに来ております。
別添 エクシードU
現行税法上、この受取人変更について課税する根拠規定はないのでこのような売り方ができるのでしょうが、個人(被保険者)が何ら保険料を負担することなく、(障害を起因とするとは言え)多額の年金受給権を無税で取得できるこのスキームを国税が放置するとは考えにくいのではないかと個人的には思います。
また、同じ障害を負ったことに対する保険金であっても、このような年金形式ではなく、一時金として法人に支払われた場合、その保険金を全額被保険者個人へ支払おうとする(例えば見舞金として)と、見舞金としての範疇を超え、給与課税されることになります。このことと平衡を取ろうとすると、やはり年金受取人の変更については課税するのが正しい、と国税は考えるのではないかと思いますがいかがでしょうか。
◎ ご指導いただいた件につきまして、先日生命保険担当者と電話で話す機会がありましたので、その後の顛末をご報告いたします。
パンフレットの商品ですが、第1回の年金が支払われた後においても(受取人変更ではなく)保険契約者の変更が可能だそうです。
よって、第1回の年金支払い後に行われる法人から個人への保険契約者変更(同時に年金受取人変更)についての課税関係は通常の保険事故発生前の契約者変更と同様に、解約返戻金相当額による評価によるべきである、との説明でした。本件保険証券については第1回支払い後の解約返戻金は0円であるので、課税は生じないとのことです。
《関連質問》
保険の税務処理について
契約者が法人、被保険者がその法人の社長、保険一時金、年金の受取人が法人となっている。
特定状態収入保障保険について、前年度に社長が重大な疾病に至り、一時金、年金の給付を受けましたが、この度年金部分の受取人を社長に変更しました。
この際の法人税、社長個人の所得税の扱いについて保険会社に問い合わせたところ、保険会社より以下の見解を得ることができました。
法人税については、年金部分を社長個人に無償で変更した場合、保険契約の譲渡となり、時価部分を役員賞与として取扱うところ、当該保険は年金部分の契約について解約返戻金がゼロ円で設定されているため、時価相当額が存在せず役員賞与が発生しない。従って特段の税務処理は必要ない。
一方、社長個人が今後受け取る年金部分については、年金の契約が特定収入状態保障保険に該当するため非課税となり、本年度を含め今後も所得税法上の申告等の必要はない。
なお、現時点において社長は月に80万円の役員報酬を得ており、年金が所得保障である側面を鑑みるに、年金部分の申告が必要ないという保険会社の見解に若干の疑念も生じております。
保険会社の法人税、所得税のそれぞれの扱いについて、どのような所見をお持ちになるか、お聞かせ願いたく存じます。
《当該保険パンフレットより一部掲載》
特定状態収入保障保険の第1回目の年金支払い日以降に受取人を変更した場合
(該当する保険種類:特定状態収入保障保険(無解約返還金)、介護年金保険(無解約返還金)、生活障害年金定期保険「エクシード」)
特定状態収入保障保険(無解約返還金)の第1回の年金支払日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合、年金を受け取る権利に対して所得税の課税は生じません。また、法人での経理処理も生じないと考えられます。
介護年金保険(無解約返還金)および生活障害年金定期保険「エクシード」の第1回の年金支払日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合の税務取り扱いも同様と考えられます。
(注)個別の税務取り扱いについては、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
“生活障害年金の受取人変更にかかる税務について” の続きを読む
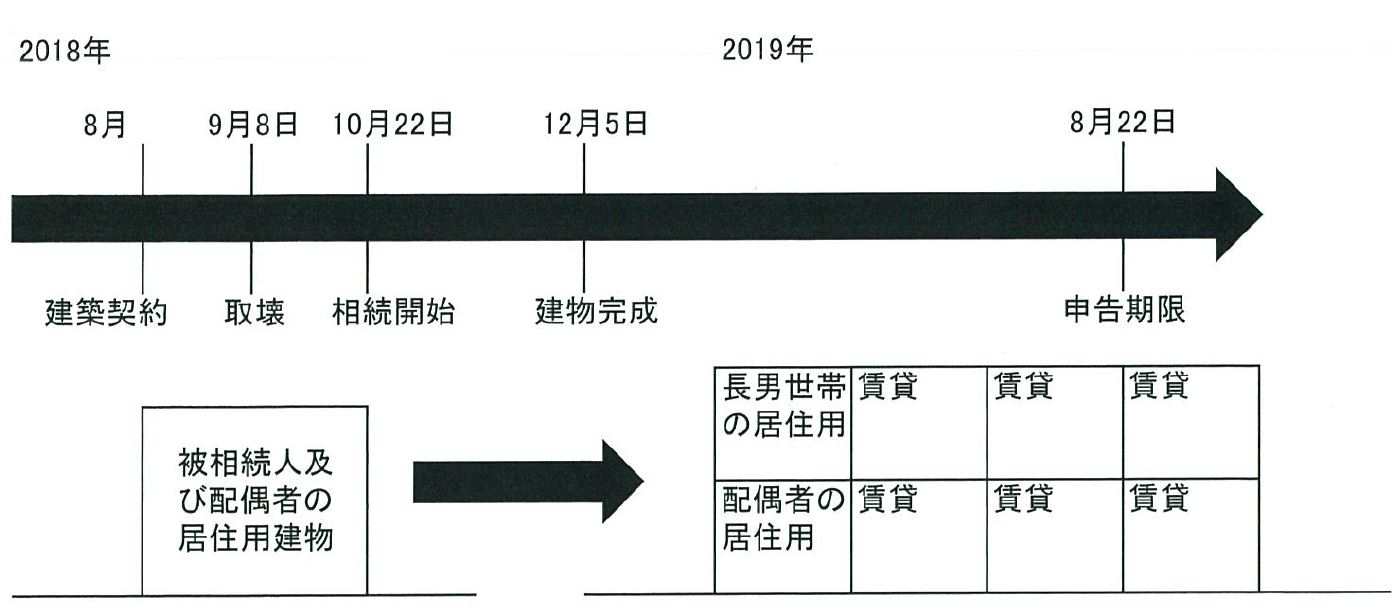 検討事項
検討事項